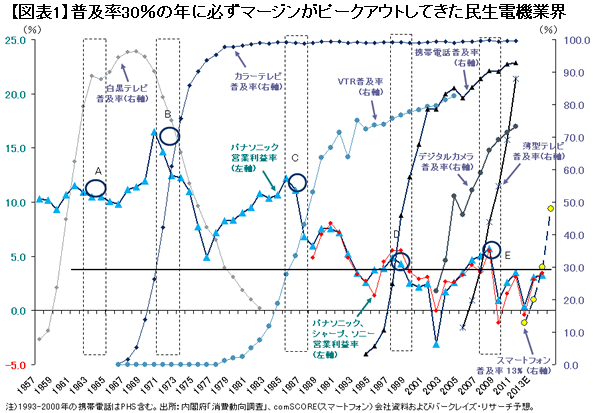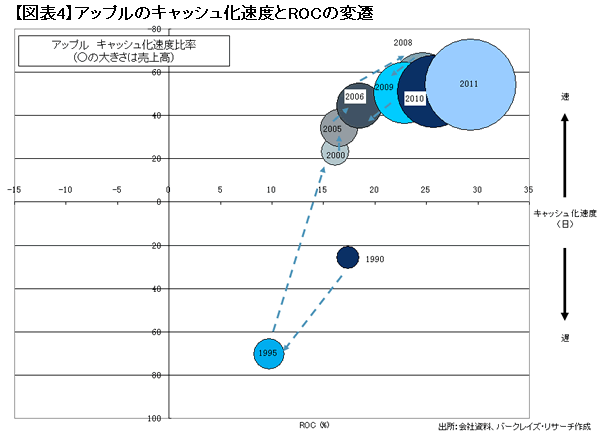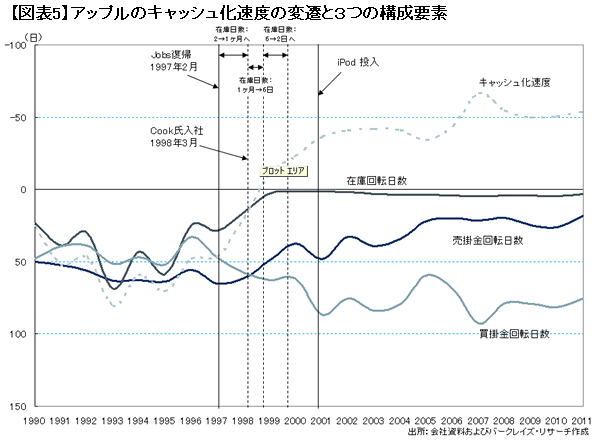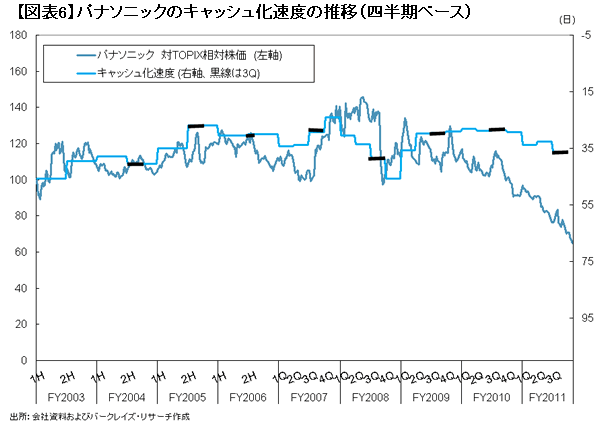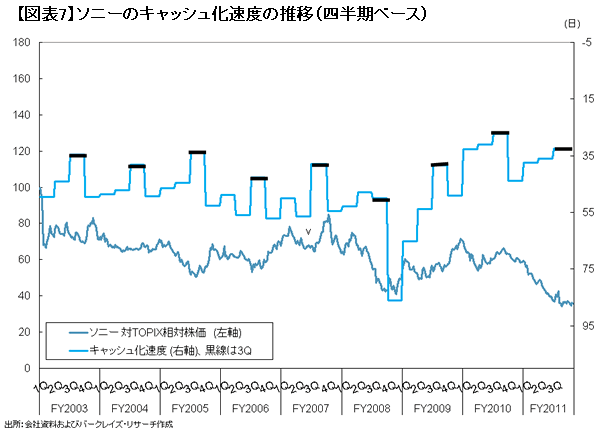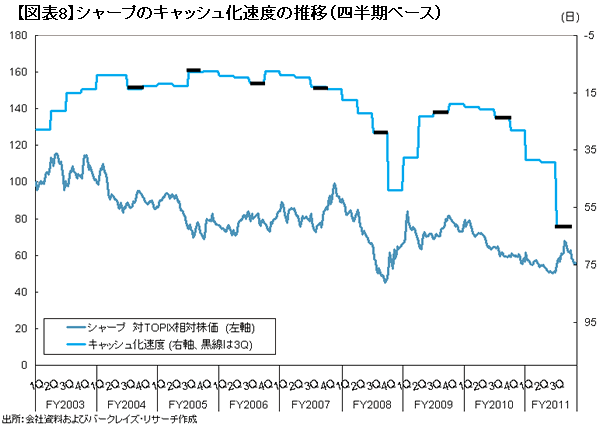【第252回】 2012年4月2日
悲劇的な決算を迎えるパナソニック、シャープ、ソニーの民生電機3社。なぜ3社はアップルになれなかったのか。スティーブ・ジョブズのように自社製品が世界をどう変えるのかという未来図(ロマン)を示し、組織を先導する強力なリーダーがいなかったというのはその答えの1つだ。しかし、他に2つある。キャッシュ化速度の違い(ソロバン)と、難局を耐え、乗り越える力(ガマン)だ。
苦境に立つ民生電機業界の真の原因は何か?
2012年3月期の合計最終赤字が1.2兆円を超える予定のパナソニック、シャープ、ソニーの民生電機3社。その凋落ぶりは指摘されて久しい。
2月以降の株価は、シャープを除けば戻り基調ながら、震災前の水準からは、約40%下回った水準で放置されている。2月1日にはソニーのハワード・ストリンガー会長兼社長が、2月28日にはパナソニックの大坪文雄社長が、3月14日にはシャープの片山幹雄社長が退任すると発表、異例の3社そろっての社長交代劇となった。
電機3社の苦戦の背景には、いくつかの要因が考えられる。そこには、1)外部要因、つまり経営陣や会社が、主体的にコントロールすることが難しい要因と、2)企業独自の失敗、いわば内部要因が混在している。
概して、経営陣のコメントからは外部要因に責任を求める風潮があり、株式市場の参加者からは内部要因に責任を求める声が多い。しかし、これらを峻別して分析することで、問題の本質を見失うことなく、今後の処方箋を考える上で有効なヒントが得られよう。
外部要因とは、経営陣が努力してもコントロールすることが難しいものである。ただし、以下で言及する為替レートや法人税負担などは、環境や制度次第で変化し得るものもある。実際、2月以降の株価の底入れの背景には、「円高の一巡」という外部要因が大きく影響したように思われる。
一方で、構造的な外部要因も存在する。以下では、「製品サイクル」の存在を構造的な外部要因と捉えて議論したい。他方で、内部要因は、企業革新によりコントロールが可能なもので、今後の新マネジメント体制下での変革に期待したい部分である。
確かに外部要因は逆風だったが…
過去5年間の為替相場を振り返ると、円はドルに対して30%円高に、ユーロに対して30%円高となった。一方、競合企業の韓国メーカーでは、ウォンコストの低下は追い風で、ウォンはドルに対し約20%減価している。
サムスンにとって100ウォン/ドルの変動は、年間約1兆ウォン強(約700億円)の営業利益の変動要因である。特に韓国内に製造拠点を有する半導体、液晶パネル、電池等のデバイスは、ウォン安のメリットを享受したことは間違いない。
また、韓国の法人税率は、住民税を足し合わせても24.2%と、日本の40.69%に比べて16%ポイント以上低い。韓国の法人税率は04年までは29.7%だったが、その後、2度にわたり減税されている。また、減価償却費に関しては、韓国では加速償却が認められており、半導体等の製造装置では償却期間が4年と、日本の5年より短いというメリットもある。
問題は構造的な外部要因「普及率30%のジンクス」は打ち破れず
一方で、外部要因の中でも、構造的な要因として、「製品サイクル」の存在を指摘することができる。
図表1は、左軸に売上高営業利益率(マージン)を、右軸に主な製品の国内普及率をプロットしたものである。マージンは、1957年度以来のパナソニックの数値と、1988年度以降はソニー、シャープ、パナソニックの加重平均した値である。超長期のトレンドとしては、残念ながらマージンは右肩下がりである(ちなみに、過去最高益は2007年度である)。
図表1のなかで重要なのは、マージンにはサイクルが存在する点だ。具体的には、主要な製品の国内普及率が30%に達した年に、必ずマージンがピークアウトするという法則が成り立ってきた。1960年度:白黒テレビ、1970年度:カラーテレビ、1984年度:ビデオデッキ、1996年度:携帯電話、2007年度:薄型テレビという具合である。
直近のマージンのピーク(2007年度)は、薄型テレビのサイクルに相当し、その後、金融危機や、エコポイント/国内でのアナログ停波特需はあったものの、2007年度のマージンを上回ることはなかった。
普及率が30%に達する時点は、技術革新による製品の付加価値の追加的な改善力が低下し、コモディティ化が本格化する時点と見なすことができる。「普及率30%のジンクス」の視点からすると、各社のTV事業の苦戦は、起きるべくして起きたと表現することができる。国内エコポイントによる需要のかさ上げにより、延命期間があった分、その反動減が大きく出たというのが、2011年度の状況ではなかろうか。
次の成長ドライバーは何か?
図表2示すように、現在のテクノロジー関連業界の成長ドライバーは、明らかにスマートフォンである。当社ではこれを、「ケータイのPC化」と表現している。つまり、ARMコアを採用した低消費電力チップの性能の向上やiOS/Androidの普及により、スマートフォンは、PCでできることをケータイで実現したのである。換言すると、クラウドを活用してPCの携帯性を高めたとも言える。
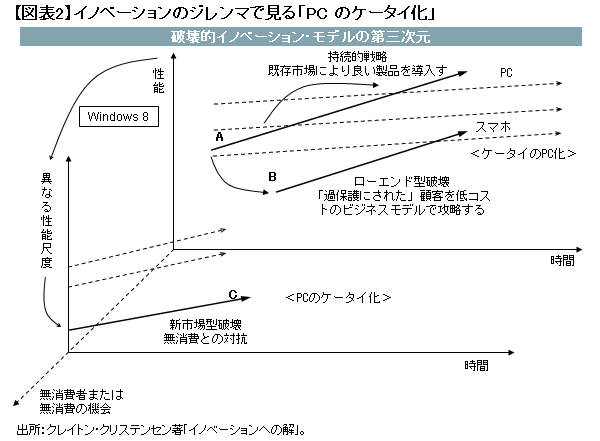
2012年のスマートフォン業界は、ローエンド端末の台頭による低価格化が進む点が懸念されているが、まだ普及率は10%強に過ぎず、「30%のジンクスの法則」に従えば、ハードウエアでの差別化が十分可能な時期にある。次世代iPhoneでのインセルタッチパネル(液晶ディスプレイ内部にタッチパネル機能を内蔵する方式。薄型化、軽量化、省電力化が可能になる)やさらなる高精細ディスプレイの採用の可能性、チップ性能の向上、サムスンのフレキシブル(壊れにくい)OLEDパネル(有機ELパネル)採用など、注目される提案もまだまだ多い。
2012年後半からはますます、「PCのケータイ化」と表現すべき潮流が本格化するだろう。2012年第3四半期末以降にリリースされる予定のWindows8は、タッチパネルやARMコアCPU採用により、省電力/薄型・軽量化を実現可能とする。スマートフォン市場で磨かれた技術が、PC市場に飛び火し、PC市場のユーザーが求める「ケータイのように、携帯性に優れる(より薄く、軽く、低消費電力)、タッチパネル採用のユーザーインターフェイスで使いやすく」を満たしていくだろう。
以上の変化は、部品コスト(BOM)の劇的な変化を生む。具体的には、CPUコストの低下、DRAM(随時書き出し、読み出しが可能な半導体メモリ)搭載容量の低下、ディスプレイの薄型/高精細化、HDD(ハードディスク)→SSD(フラッシュメモリドライブ)への切り替え、リチウムイオンポリマー電池の普及、クラウド対応投資の増加などである。
もちろん、消費者にとっては価格が低下するメリットをもたらすし、新しいサービスやアプリケーション・ソフトの登場も期待できる。以上の変化から、エレクトロニクス業界の主要プレイヤーのポジションが激変する可能性がある。
分かれる3社の進路
次の成長サイクルを前に、3社の戦略は異なる。
ソニーは、10億5000万ユーロを投じて、携帯/スマートフォン事業を手がけるソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズを100%子会社化し、この新サイクルに積極的に乗る戦略を採った。3月27日に発表された新体制では、鈴木国正氏の傘下で、スマートフォン、タブレット、PCなどは一括して管理する体制に移行する。モバイル領域は、ソニーの元来のDNAであり、避けては通れない領域だ。今期のスマートフォン事業は、テレビ事業を抜いて最大の事業規模となる可能性もあり、スマートフォンの成否はソニーの成否に直結する。
シャープは、アップルなど主要メーカーへの液晶パネル供給を通じて、消極的に新サイクルに乗る戦略と見ることができる。ディスプレイの薄型/高精細化のニーズの高まりは、シャープの既存の液晶パネル工場の付加価値を上げる潜在力を有する。14型モニター用パネルの価格は40ドル程度だが、13.3型ノートPC用の高精細パネルの価格は130ドル程度の模様だからである。課題は、大口顧客の確保と、モジュールを含めたソリューション型ビジネスへの転換力だろう。
3月27日に発表された鴻海グループとの戦略的提携は、ディスプレイの薄型/高精細化のニーズを取り込むチャンスを高める可能性があると思われる。技術流出を危惧する声もあるが、シャープの生産技術と鴻海グループのモジュール技術や顧客関係を連結することで、サムスン電子など韓国メーカーに対抗しうる体制が整うこととなる。
一方、パナソニックは、スマートフォンのサイクルで戦うことを諦め、白物家電や車載用バッテリー、B2B事業、“まるごとソリューション”など、異なる土俵で戦う戦略である。スマホの欧州展開などは行うが、あくまで事業ドメインの個別最適の戦略と見なすことができる。
各社の戦略の成否は、歴史が証明することとなるだろうが、以下のような内部要因の解決なくして、成功はおぼつかない。
民生電機業界の苦戦の背景にある内部要因とは?
内部要因には、1)意思決定システムの制度疲労ともいうべきガナバンスの問題と、2)企業価値の創出を意識したキャッシュ・フロー管理力の欠如があったように思われる。ガナバンスの問題は、経営トップの責任論のみならず、いわば、既存の事業部や子会社群の枠組みを超えて新しい顧客を生み出すという本来のマーケティング発想の欠如も含まれる。
一方、キャッシュ・フロー管理力に関しては、合理的な投資意思決定プロセスの欠落、完結できなかった事業プロセスの見直しなどが、課題視されるべきだろう。
内部要因の1)に関しては、創業経営者の時代、つまりビジョナリーが夢の実現のために進路を示し、全社がそのビジョンに向かって結束していた時代には問題になることはなかった。
今日の日本企業は、米アップルの故スティーブ・ジョブズ氏や、サムスン電子のイ・ゴンヒ氏のように、創業者が君臨する企業の強みを噛みしめているだろう。この課題は、言い換えると「ロマン」の欠如である。時代の先を読んでいたはずのソニーが、なぜアップルに先を越されたのか?ビジョン不足の体制下で、事業部最適の弊害、事業部と販売部門との収益管理責任の不整合、OSの選定などでの意思決定の遅延などが克服できなかったのだろう。
従って、内部要因の2)が非常に重要になる。当社ではこれを「ソロバン」の問題と捉えている。
例えば、パナソニックの三洋電機の買収価格は、他社の過去の事例などに比べて割高との指摘があった。PDP(プラズマディスプレイパネル)事業への過度な傾斜と、その後の液晶パネル工場への投資も、軌道修正はもっと早くできたはずだ。シャープの10G工場への投資も、経済合理性を超えた要因はなかったか。当時、サムスン電子などライバルメーカーは、60型以上の世界のテレビ需要を精査し、堺工場(10G:第10世代)工場の建設には経済合理性が乏しい点を見抜いていたのだから。
キャッシュ化速度に注目
弊社では、「ソロバン」の重要性を見る上で、「キャッシュ化速度」の変化に注目している。
キャッシュ化速度とは、運転資本の回転日数を表したもので、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)と同じものだが、パナソニックの「中村改革」の知恵袋として活躍した経営コンサルタントのフランシス・マキナニー氏が、Velocity of Cash(現金の流通速度)と命名したのが語源である。キャッシュ化速度は、以下の式で定義される。
「売上債権回転日数+在庫回転日数-買入債務回転日数」
キャッシュ化速度を改善するには、在庫削減は当然ながら、売上債権や買入債務の「サイト」を変更する点に議論が偏りがちである。但し、本当に重要なのは、業界全体のキャッシュ化速度、言い換えるとサプライチェーンを効率化するかという視点である。マキナニー氏が、Velocity of Cashとあえて呼んだのには、こうした含意がある。
例えば、いわゆる中村改革を通じて02年~06年までキャッシュ化速度を大きく改善させたパナソニックでは、マーケティング会社に仕入れ権限を持たせた流通改革、製品の世界同時立ち上げ、そのためのソフトウエアのプラットフォーム化などを行った。パナソニックは、中小部品メーカーに対しては、現金で支払うという伝統を堅持してきた会社で、サイトの変更によってキャッシュ化速度を改善することは最近までは行っていない。
図表3では、主要企業の2010年度の数字を対象に、縦軸にキャッシュ化速度を、横軸に投下資本利益率(ROC=Return On Capital)をプロットしたものである。円の大きさは売上規模を表す。キャッシュ化速度は上へ行くほどマイナスとなる。つまり速くなるということだ。
縦軸と横軸は、「税引後営業利益+減価償却費等-設備投資-運転資本の増減」で定義されるフリー・キャッシュフローを代弁している。つまり、ROCは投資効率を、キャッシュ化速度は運転資本の増減を表現し、図表の右上へ行くほど、企業のフリー・キャッシュフロー創出力は高まる。
なぜキャッシュ化速度が大事なのか?
キャッシュ化速度が重要な理由は3つある。第1に、キャッシュ化速度は、事業プロセスに根ざし、その変化そのものがバリューチェーンの再構築の結果として表れる。つまり、キャッシュ化速度の変化は持続性を有する。
人員削減や設備の減損は、一時的に人件費や償却費の利益化につながり、ROCは右方向へシフトするが、これには持続性はない。「良いリストラ」と「悪いリストラ」を見分けるためにも、キャッシュ化速度は重要なのだ。
第2に、キャッシュ化速度は、運転資本の増減というフリー・キャッシュフローの構成要素であり、企業価値に直結する。例えば、売上拡大やマージン改善は、企業価値の構成要素であるフリー・キャッシュフローに間接的に影響する。だが、十分条件ではない。
第3に、キャッシュ化速度は日数で表現されるために、外部環境(市場成長率や為替など)に左右されにくい。売上が減る局面でも在庫削減に努めることで、日数ベースでは管理が可能である。多くの企業が中期経営目標として発表する売上高や利益額、ROEなどの目標は、外部要因で簡単に変化してしまうが、本来、企業は管理可能な数字にコミットすべきだ。
特筆に値するアップルのキャッシュ化速度
アップルの成功は、革新的な製品によって導かれたと一般には信じられている。しかし実は、アップル成功の背景には、キャッシュ化速度改革が存在する(図表4)。
今でこそアップルは、マイナスのキャッシュ化速度を持つが、過去はそうではなかったからだ。ちなみに、キャッシュ化速度がマイナスということは、例えばiPadが実際に売れて売上が立つ前の段階で、すでに仕入れ代金は回収できている、ということだ。図表5は、アップルのキャッシュ化速度を、3つの構成要素に分解し、時系列で見たものである。ジョブズ氏が1997年2月に復帰、ティムクック氏が98年3月に入社した頃から、アップルのキャッシュ化速度は劇的な改善を見せる。
具体的には、製品数の削減、自社工場の削減とODM(相手先ブランドによる設計製造)メーカーの活用による在庫の短縮、主要サプライヤーの削減(100→24社へ)、PCの開発期間の短縮化、生産ロットの大規模化や発注精度の改善による部品メーカーとの取引条件の改善を断行した。コストアップ覚悟で、製品を空輸する手法や、当初はキャッシュ化速度の改善にはつながらなかったが、その後大きな成果を生む自社小売店舗網への投資もユニークな戦略だった。
ちなみに、08年時点でアップルは全米第3位の家電小売り業となっている(1位はベストバイ、2位はウォルマート)。小売業は現金回収が早いのみならず、需要をコントロールできるというメリットがある。サプライチェーン改革の要諦は、需要を正確に予測することであり、アップルは「デマンドチェーンの構築」という基本に忠実な戦略を断行した。
大事なのは、iPodの発売される01年以前に、上記のようなキャッシュ化速度を早めるための事業プロセス改革が進んでいた点だ。キャッシュ化速度がマイナスならば、在庫リスクを気にすることなく新製品を投入でき、ヒット商品を生み出す確率が高まる。これらの改善が、iPodやiPhoneというモンスター商品を生み出した要因の一つであろう。ソニーのケースでは、ゲームのハードウエアを除けば、1つの製品で月産100万台規模の新製品を製造することはまずない。
日本企業の現状
パナソニックは中村改革を通じてキャッシュ化速度の改善に成功した。中村改革はキャッシュ化速度改革であり、軽くて速い会社を目指した改革は、マキナニー氏が問う「サッカーボール理論」を体現した改革だった。但し、大坪社長が就任した06年以降は劇的な改善はなくなり、直近ではキャッシュ化速度が低下し始めている(図表6)。
一方でソニーである。出井改革以降で行われた構造改革では、人員削減など目先の経費削減の域を出なかったため、運転資本の改善はあまり見られなかった。但し、08年以降は、調達改革や工場の売却を通じて、事業プロセスに変革の兆しが見えていた。現状は、液晶テレビの在庫増に直面し、踊り場にある。
シャープのキャッシュ化速度は、05年度にピークを迎えている。その後に改善を見せた時期はあったが、堺工場の設備手形の増加が背景にあり、実体は悪化を続けていたと見ることができる。工場の稼働を起点とする事業モデルにより、工場稼働率の維持のために、在庫は増加し続け、ソフトランディング・シナリオは完全に頓挫してしまった(図表8)。
まずはソロバン改革から
アップルのように事業プロセス改革に成功したものの、その後、業績の低迷を余儀なくされた企業の代表例がデルである。だからといって、ビジョナリーの個人能力に頼ることが難しい日本企業の現状では、「ロマン」に依存する戦略は機能しないだろう。まずは、「ソロバン」の改革、つまりキャッシュ化速度のアップにつながる事業プロセス改革を行うべきではないか。
「ソロバン」の改革は、単なる固定費削減とは異なる。キャッシュ化速度改革によって、既存の低成長事業からもフリー・キャッシュフローを生み出し、その原資を持って次のチャレンジを可能にするものである。ロマンとソロバン、そしていま、何よりも大事なのは「ガマン」して難局を乗り切る覚悟だろう。